親世帯と子世帯が一緒に住む二世帯住宅は、家族のつながりを大切にしながら、プライバシーも守れる暮らしのスタイルとして人気があります。
けれども、いざ建てるとなると気になるのが、住宅ローンの組み方ではないでしょうか。名義は誰にするべきか、どのくらい借りられるのかなど、不安も多いでしょう。
そこで今回は、二世帯住宅ならではのローンの種類や名義の考え方、無理のない返済計画の立て方をわかりやすく解説します。
二世帯住宅のローンの組み方|代表的な3つの方法
二世帯住宅は、建築費用が高額になりやすいため、親子で協力してローンを組むケースが多くなります。
その際に活用される代表的なローンの組み方が、以下の3つです。
1.収入合算ローン|親子で収入を合わせて借りる
「収入合算ローン」は、親子それぞれの収入を合算し、借入可能額を増やす方法です。
住宅ローンの名義人は1人ですが、もう一方の収入も審査に加味されるため、借入上限を引き上げられるのがメリットです。
ただし、合算者は「連帯保証人」または「連帯債務者」となり、返済義務が発生します。
名義人を誰にするか、将来的な相続や持分の取り扱いも踏まえて、慎重に検討しましょう。
2.親子ペアローン|それぞれが別々のローンを組む
「親子ペアローン」は、親と子がそれぞれ別の住宅ローン契約を結び、2本同時に借りるスタイルです。
それぞれの名義で借り入れるため、双方が住宅ローン控除を受けられる可能性があるという大きなメリットがあります。
一方で、2本のローンを同時に管理する必要があり、手続きや金利プランの選定には手間がかかります。また、どちらかの返済が滞るともう一方に影響が及ぶため、家族間での信頼関係と役割分担が重要です。
3.親子リレーローン|返済を親から子にバトンタッチ
「親子リレーローン」は、ローンの返済を親から子へと引き継いでいく仕組みです。当初は親が主に返済を行い、親の収入がなくなったタイミングで、子どもが返済を引き継ぎます。
この方法の最大の特徴は、高齢の親でもローンを組みやすい点です。完済時年齢が引き上げられるため、親の年齢がネックになるケースでも対応できるでしょう。
ただし、返済期間が長期化しやすく、親子の両方に責任が生じるため、将来設計や相続への影響も含めて検討が必要です。
ローンの名義・持分はどうする?単独名義と共有名義の違い
二世帯住宅の住宅ローンを組む際に見落としがちなのが、「名義」と「持分」の考え方です。
誰の名義で登記するか、どのように持分を分けるかによって、住宅ローン控除や将来の相続、税金にまで影響を及ぼします。
家族間の信頼関係があっても、お金の問題は難しく、あとからトラブルになったというケースは少なくありません。あらかじめ正しく仕組みを理解しておくことが、将来の安心にもつながります。
登記の方法によって税制上の扱いも変わる
建物を誰の名義にするか、つまり登記名義人をどうするかは、非常に重要なポイントです。
単独名義にすると、その人がすべての権利を持つことになり、住宅ローン控除などの税制優遇も名義人しか受けられません。一方、共有名義にすれば、持分に応じて複数人で権利を持つことができ、それぞれが控除を受けられる可能性があります。
ただし、共有名義にするには、登記上の持分割合と実際の出資額が一致していなければ、贈与とみなされて課税されるリスクもあるのです。また、共有名義は後々の売却や相続で意見が分かれる原因にもなります。
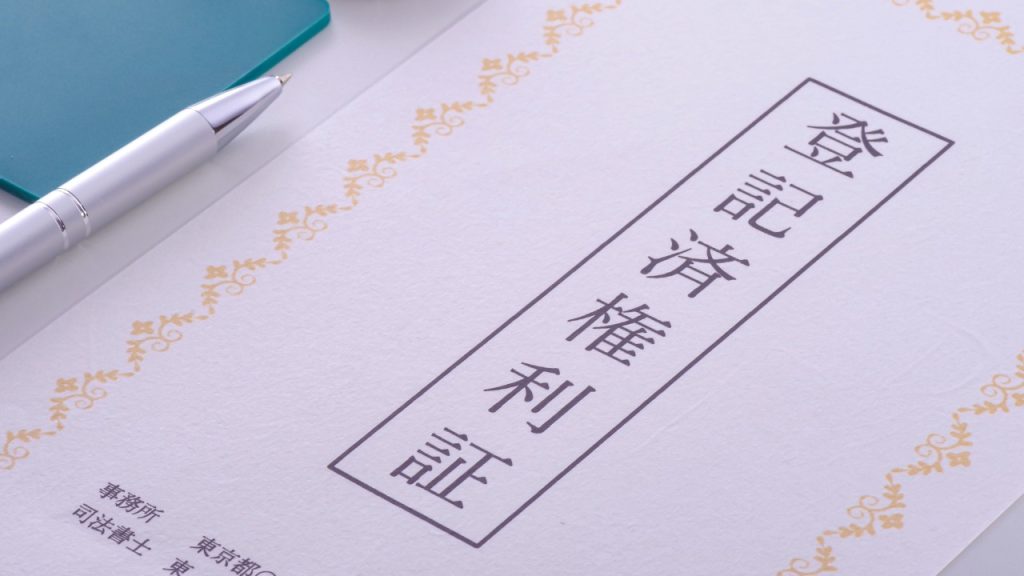
●ポイント: 単独名義は管理が楽。共有名義は税制メリットがあるが、慎重な設計が必要
持分割合と住宅ローン控除の関係
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるには、ローンの名義、登記の持分、実際の返済負担が一致している必要があります。
たとえば、
・持分50%ずつでローンも折半している → 双方で控除が可能
・名義だけ共有で、実際の返済は片方のみ → 返済していない側は控除を受けられない

●ポイント:控除を受けたい人は、持分・返済実績・名義のすべてが一致していることが条件
ケース別|どのローンが適しているか?
二世帯住宅のローン選びは、家族の状況やライフステージによって最適な方法が異なります。
親が高齢で年金暮らしの場合:親子リレーローン
親がすでに退職していて年金生活の場合、一般的な住宅ローンでは審査に通らないことがあります。
その場合に選ばれやすいのが、「親子リレーローン」です。
親の年齢が高くても、子世帯に返済が引き継がれる前提で借入できるため、完済年齢の制限を超えてもローンを組める可能性があります。
ただし、親が連帯債務者になる場合も多く、親が亡くなった後の名義変更や相続処理が複雑になるケースもあるため、事前に家族でしっかり話し合っておきましょう。

●注意点: 相続時の登記・返済の引き継ぎ
子世帯の収入が不安定な場合:収入合算ローン
転職したばかり、フリーランス、産休・育休中など、子世帯の収入が安定していない場合は、単独での借入が難しいこともあります。
このようなケースでは、「収入合算ローン」が有効です。親の安定した収入(年金や勤続実績)が審査に加味されることで、借入可能額を引き上げられます。
ただし、名義人は1人に限定されるため、控除や持分に関しては後述の税制ルールを確認しておきましょう。

●注意点:名義と実際の返済額の整合性を確認
相続人が複数いる場合の注意点:ペアローンまたは持分調整+法的対策
兄弟姉妹など、相続人が複数いる家庭では、ローンの名義や登記の仕方がトラブルの原因になることがあります。
たとえば、親子でローンを組んで親の名義で家を建てた場合、親が亡くなった後に「他の兄弟にも相続権がある」として揉めることも考えられます。
こうした事態を避けるには、以下の対策を検討してください。
・持分を最初から明確に分けておく
・親子ペアローンや共有名義にしておく
・遺言書や生前贈与などの準備をする
特に親がすべてを負担したような形に見える場合は、相続税や贈与税のリスクも含めて慎重に計画しましょう。

●注意点:登記と相続が一致していないと争いの火種になりやすい
無理なく住宅ローンを返済するためのポイント
二世帯住宅のローンは金額が大きくなりやすいため、「いくら借りられるか」ではなく「いくらなら無理なく返せるか」を基準に計画を立てることが大切です。
ローン返済を長く安定して続けていくための4つのポイントをご紹介します。
1.頭金の目安とタイミング
頭金は、大きければ大きいほど、ローンの返済が楽になります。
一般的に住宅購入時の頭金は「物件価格の2〜3割」が目安とされていますが、二世帯住宅の場合は建築費用が高くなりやすいため、できればそれ以上の準備が望ましいでしょう。
また、親世帯が頭金を出すケースもありますが、そのままでは贈与税が課税される場合があるため、持分の設定や契約書類の整備が必要です。

2.固定金利と変動金利の選び方
住宅ローンを組む際には、固定金利か変動金利かを選ぶ必要があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、家族のライフプランに合わせた選択が重要です。
・固定金利:返済額が一定で将来の見通しが立てやすい。金利がやや高めでも、長期的な安定を重視したい方におすすめ
・変動金利:金利が低く、初期の返済負担が軽い。将来金利が上昇すると返済額が増えるリスクがあるため、短期間で返済を終える予定の方向き
特に二世帯住宅では、親世帯が高齢で退職済みなどの場合、固定金利を選ぶことで計画が立てやすくなることもあります。

3.返済負担率を意識した借入額の設定
「返済負担率」とは、年収に占める年間返済額の割合のことです。一般的に返済負担率は「年収の25〜30%以内」が目安とされており、これを超えると家計への負担が大きくなり、生活が苦しくなる可能性があります。
とくに、子世帯に教育費・親世帯に医療費など、将来的な出費が予想される場合は、余裕をもった設定が必要です。

4.将来のライフスタイルの変化に備える
住宅ローンは、最長で35年におよぶ長期の契約ですから、その間には、家族構成や収入状況の変化、転職や独立、介護や子育てなど、さまざまなライフイベントが訪れます。
こうした将来の変化に備え、繰り上げ返済や借り換え、団体信用生命保険の見直しなど、柔軟に対応できるよう準備しておくことも大切です。
また、親が亡くなった場合の相続や家の処分についても、事前に話し合っておくことでトラブルを防げます。

二世帯住宅のご相談は石井工務所へ
二世帯住宅を建てるとなると、現在の家族構成だけでなく、将来のライフスタイルまで見据えた設計が必要です。インターネットで調べただけでは判断が難しいことも多く、専門的な知見が必要です。
石井工務所では、みなさまの理想をかなえるために、家づくりのプロとしてさまざまな提案を行ってまいりました。
・こんな家を建てられる?
・オリジナルのデザインで、地震に強い安全な家にしたい
・建てた後もメンテナンスしてもらえる?
など、ご要望があれば、どのような小さなご質問でもお答えいたします。
具体的な事例をもとにアドバイスさせていただきます。家族みんなが安心して暮らせる住まいを実現するために、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
まとめ
二世帯住宅のローン計画は、通常の住宅購入よりも複雑になりがちです。
収入の合算方法や名義の設定、税制優遇の活用、将来の相続への備えなど、考えるべき要素は多岐にわたります。
しかし、事前にしっかりと情報を整理し、家族で話し合いを重ねることで、無理のないローン返済と快適な二世帯暮らしの両立は可能です。
ポイントは、家族構成や生活設計に合わせて柔軟に考えることです。ライフステージの変化にも対応できる計画を立てて、安心・快適な住まいづくりを進めていきましょう。
