二世帯住宅を建てると、親世帯・子世帯それぞれに安心できる暮らしが叶うだけでなく、税金の面でも思わぬメリットがあります。
固定資産税や不動産取得税の軽減、住宅ローン減税の適用、さらには相続や贈与に関する優遇まで、二世帯住宅ならではの制度を知っておくことで、家計の負担を大きく減らすことができるのです。
ただし、二世帯住宅のタイプや登記の方法によっては、優遇が受けられないケースもあるため注意が必要です。
そこで今回は、二世帯住宅にかかる税金の基本と軽減措置について、わかりやすく解説します。これから二世帯住宅を建てようと考えている方はぜひ参考にしてください。
二世帯住宅にかかる税金の基本
二世帯住宅を建てる際には、一般的な住宅と同じようにいくつかの税金が発生します。主に、以下の税金と関わりがあります。
【不動産取得税】
新しく不動産を取得したときに一度だけかかる税金です。建物の床面積や評価額によって金額が変わりますが、一定の要件を満たすと軽減されます。
【登録免許税・印紙税】
登記をするときや契約書を交わすときに必要となる税金です。登記の方法や持分割合によっても金額が変わるため、二世帯住宅では注意が必要です。
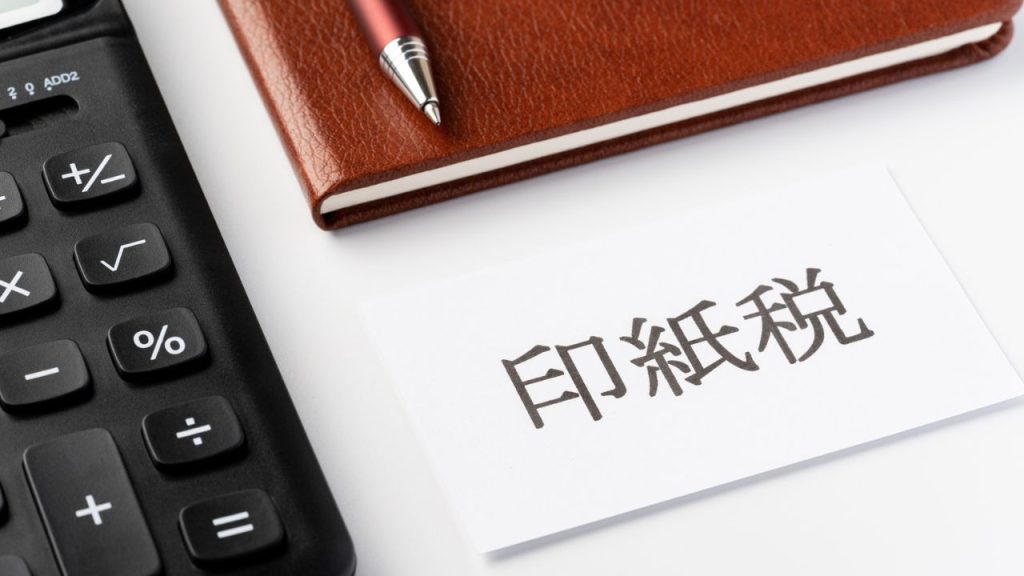
【固定資産税】
土地や建物を所有している限り、毎年かかる税金です。建物の評価額に応じて計算され、新築住宅の場合は一定期間、軽減措置が受けられる場合があります。
【所得税(住宅ローン減税)】
住宅ローンを利用して建てる場合、年末のローン残高に応じて所得税や住民税から控除を受けられる制度です。二世帯住宅でも要件を満たせば適用できます。

二世帯住宅を建てると軽減される税金の例
二世帯住宅を建てると、通常の住宅と同じくいくつかの税制優遇が受けられますが、工夫次第でさらに税金を軽減することも可能です。
ここでは代表的な軽減措置を見ていきましょう。
固定資産税の軽減措置
新築住宅には、居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下で、住宅として使用する部分が全体の床面積の1/2以上であれば3年間(長期優良住宅なら5年間)、固定資産税が2分の1に軽減される制度があります。
二世帯住宅でも、この要件を満たせば同じように適用されるため、設計段階で床面積を確認しておくと安心です。
(参考:「新築住宅に係る税額の減額措置」

不動産取得税の軽減措置
不動産を取得したときにかかる不動産取得税は、住宅用の建物や土地について軽減措置が設けられています。建物については床面積50㎡以上240㎡以下であれば特例が適用され、1世帯1,200万円が控除されます。
二世帯住宅の場合、居住要件を満たせば、1,200万円×2世帯分の控除が受けられます。
(参考:「不動産取得税に係る特例措置」

住宅ローン減税(所得税の控除)
住宅ローンを利用して建てた場合、年末のローン残高に応じて所得税や住民税から控除が受けられる住宅ローン減税制度があります。
住宅ローン減税を受けるには、 50㎡以上で、かつ、居住空間が1/2以上という条件がありますが、共有登記もしくは区分登記をしていれば、それぞれの世帯で控除を受けられます。
(参考:「一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
相続税の小規模宅地等の特例
「小規模宅地等の特例」とは、相続が発生したときに居住用の土地の評価額を最大80%減額できる制度です。二世帯住宅も、同じ敷地内で生活していることや、相続人が相続後も住み続けることなどの条件を満たせば、この特例措置の対象となります。
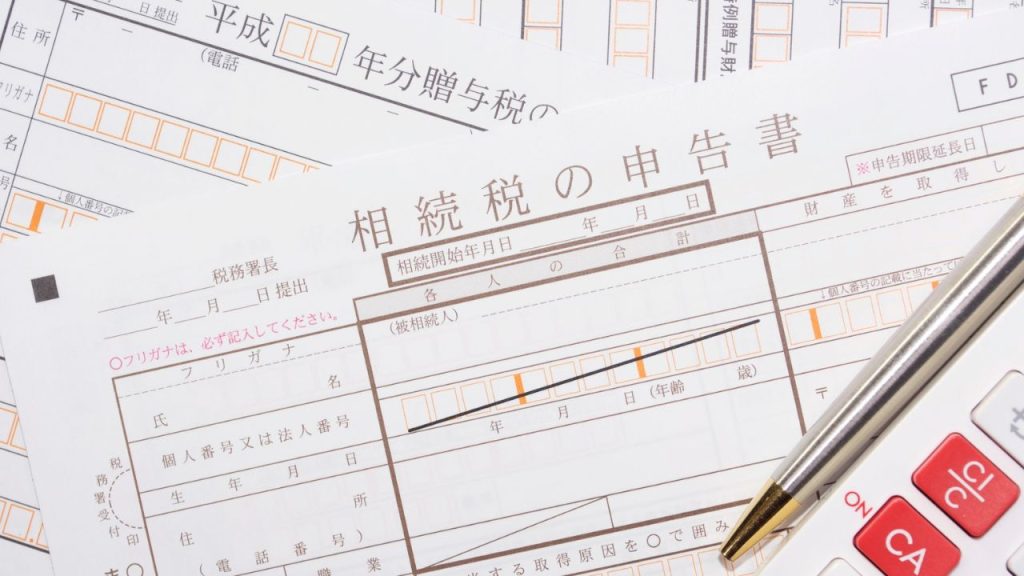
二世帯住宅のタイプ別に違う税金の扱い
二世帯住宅には、主に3つのタイプがあります。
このタイプの違いが、受けられる税金の優遇に影響することがありますので、注意したいところです。
【完全分離型】
玄関・キッチン・浴室などすべてを親世帯・子世帯で分ける完全分離型は、税制面でも独立した住宅として扱われやすいのが特徴です。登記を分ければ、親世帯と子世帯がそれぞれ住宅ローン減税を利用できる場合もあります。将来の相続でも「小規模宅地等の特例」が適用されやすく、安心感の大きいタイプです。
【部分共有型】
玄関は別々でも浴室やキッチンは共用、または玄関は一つでも内部で区切られているといった部分共有型。暮らしやすさとプライバシーのバランスが取れる反面、税制優遇は完全分離型ほど幅広くありません。住宅ローン減税は条件によって適用が制限されることがあるため、登記の仕方が重要になります。
【完全同居型】
玄関も設備も一つにまとめ、親世帯・子世帯が同じ家で暮らす完全同居型は、税金面では一般的な一世帯住宅と同じ扱いになります。二世帯住宅特有の優遇は受けにくいものの、建築費用や維持費を抑えられる点が魅力です。
贈与税や相続税の非課税枠の利用方法
世帯住宅を建てる際には、建築資金を親子で出し合うケースも多くあります。
そのときに気になるのが「贈与税」や「相続税」ですが、上手に制度を利用すれば税金の負担を大きく抑えることができます。
住宅取得資金贈与の非課税枠
父母や祖父母から住宅取得のために資金援助を受けた場合、条件を満たせば 最大1,000万円程度(省エネ住宅や耐震住宅は上限が高め)まで非課税となることがあります。
二世帯住宅の場合、親からの援助で子世帯の住宅部分を建てるとき、この非課税枠を利用できます。

相続時精算課税制度
こちらは「いま贈与してもらったお金は、とりあえず非課税。将来の相続のときにまとめて精算しましょう」という仕組みです。
2,500万円までの贈与について贈与税がかからず、相続のときに精算します。二世帯住宅の建築資金を親世帯から援助してもらうときに使われることが多く、将来の相続税対策としても有効です。
贈与時に大きな税負担が発生しないため、「資金繰りがしやすい」というメリットがありますが、一度この制度を選ぶと暦年贈与(110万円の非課税枠)に戻せないため、将来の相続全体を考えた上で利用する必要があります。
(参考:「相続時精算課税の選択」
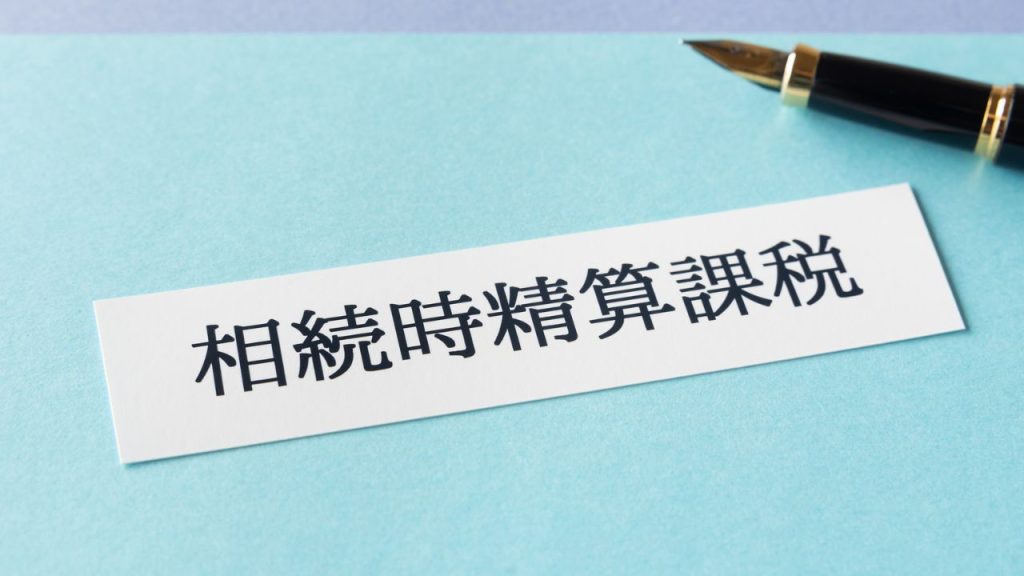
二世帯住宅で税金の軽減措置を受けるために注意したい登記の方法
二世帯住宅で税制優遇を受けるには、「どのように登記をするか」も重要なポイントになります。登記の仕方次第で、住宅ローン減税や相続税の特例が使えるかどうかが変わるため、慎重に検討する必要があります。
持分割合の設定
親世帯と子世帯が一緒に資金を出し合って二世帯住宅を建てる場合、出資額に応じて「持分割合」を登記するのが基本です。
この持分がしっかり登記されていれば、自分が負担した部分について住宅ローン減税を受けられるほか、将来の相続でも「誰がどれだけ所有しているか」が明確になるため、トラブルを防ぐことができます。

登記を分けるか分けないか
完全分離型の二世帯住宅では、建物を2つの住戸として登記を分けることができます。
この場合、親世帯・子世帯がそれぞれの住戸を「自分の家」として所有し、別々に住宅ローンを組めば、両方が住宅ローン減税を受けられる可能性があります。
一方で、部分共有型や完全同居型のように建物を分けにくい場合は、登記もひとつにまとめられることが多く、その場合は減税措置が親世帯か子世帯のどちらか片方にしか適用されないケースもあります。

将来を見据えた登記方法の選び方
登記の仕方は、相続や贈与のときの税負担にも直結します。
たとえば、子世帯の持分をきちんと登記しておけば、親が亡くなった後もスムーズに相続でき、余計な税金を払わずに済む可能性があります。
逆に「すべて親の名義」で登記してしまうと、実際には子もお金を出しているのに住宅ローン減税を受けられず、さらに相続のときに税負担が大きくなるリスクもあるのです。
登記は一度行うと後から変更するのが難しいため、建築段階でしっかり検討しておくことが大切です。資金計画や将来の相続まで視野に入れ、専門家に相談しながら最適な方法を選びましょう。
注文住宅で不安なことは石井工務所へご相談ください
二世帯住宅を建てるにあたっては、税制の優遇や登記方法など、間取り以外にも考えることがたくさんあります。制度を活用すれば家計の負担を減らせますが、条件や手続きは複雑で、不安に感じる方も多いでしょう。
石井工務所では、これまで数多くの二世帯住宅を手がけてきた経験をもとに、設計段階から安心して進められるよう丁寧にサポートしています。
お客様の理想を最大限取り入れながら、ご家族が安心・安全に暮らせる住まいづくりのお手伝いをしています。
二世帯住宅に少しでも不安を感じたら、まずはお気軽に石井工務所にご相談ください。
まとめ
二世帯住宅は、暮らしの安心を守りながら、固定資産税や不動産取得税の軽減、住宅ローン減税、さらには相続や贈与に関する特例まで、さまざまな税制優遇を受けられる可能性があります。
ただし、住宅のタイプや登記の仕方によっては適用されないこともあるため、制度を正しく理解して準備することが大切です。
家族の将来を見据え、安心して暮らせる二世帯住宅を実現するためには、経験豊富な建築会社や専門家のサポートを受けることが一番の近道です。制度を上手に活用して、安心で無理のない住まいづくりを進めていきましょう。
